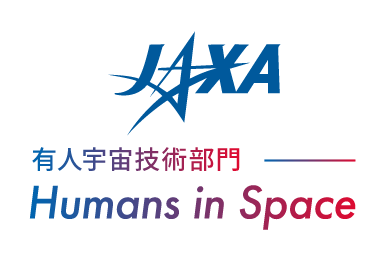JAXA大西卓哉宇宙飛行士による帰国後記者会見
今年(2025年)3月から8月まで、約146日間宇宙に滞在した大西宇宙飛行士が、帰還後のリハビリを終えて一時帰国。10月3日に長期滞在ミッションに関する記者会見を行いました。

大西宇宙飛行士冒頭の挨拶(抜粋/要約)
本日はお忙しい中、記者会見にお集まりいただいた皆さま、またYouTubeでご覧の皆さま、誠にありがとうございます。私は、国際宇宙ステーションに約5か月間、長期滞在をしてまいりました。たくさんの関係者の方々に支えられて無事にミッションを遂行し、8月9日(アメリカ時間)に、地球に無事帰ってくることができました。支えてくださったたくさんの方々に、改めてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。約5か月間の滞在で、身体が宇宙仕様になっていましたので、帰還後は45日間という時間をかけて、地上仕様に戻すリハビリテーションに取り組んでまいりました。1回目のフライトと比べると、私自身の経年劣化がだいぶ進んでいたこともあり、リハビリは前回と比べると大変な思いをしましたが、身体の運動機能としては、ほぼ元に戻った状態かと思っています。一方で、例えば椅子に座っている状態だと、しばらくするとお尻が痛くなったり、長い時間歩いていると足の裏が痛くなったりと、宇宙空間ではやらないような動作に関しては、まだ少し違和感が残っています。宇宙からの帰還後、初めて日本に帰国し、今後は記者会見やさまざまな取材、ミッション報告会などの対応を予定しております。また、地上のエンジニアやフライトコントローラ(運用管制員)の方々との技術的なデブリーフィングも行う予定になっております。
この後、大西宇宙飛行士から、第72次/73次長期滞在における軌道上での活動成果について、映像を交えながら説明が行われました。

質疑応答(抜粋/要約)
ー大西宇宙飛行士は、今回のISS滞在中、「走らない研究」に参加されたと伺いましたが、その狙いや目的を教えてください。
まず前提として、国際宇宙ステーション(ISS)に長期滞在する宇宙飛行士は、微小重力環境で筋肉や骨が弱ったり心肺機能が低下したりするのを防ぐために、「筋トレ」と「有酸素運動」を行います。そして、有酸素運動には通常、トレッドミルという走るための機械と、自転車のようにペダルを漕ぐ機械の2種類を使用します。ただ今回私は、「走らない研究」に被験者として参加していたため、トレッドミルは一切使わず、自転車型の機械だけで有酸素運動を行いました。この研究の背景にあるのは、将来の月や火星探査です。月や火星へ向かう宇宙船や探査用の有人与圧ローバーは容量がさほど見込めないため、トレッドミルのような大型の装置を持っていくのは困難です。そこで「走ることができない環境」を想定して、人間の筋力や持久力がどうなるのか、精神面への影響はあるのか、といったことを調べているわけです。今回はかなり有用なデータが取れたのではないかと思っています。被験者の一人として、研究の最終的な結果を楽しみにしているところです。
ーISSでの生活を経験されて、月や火星探査に向けて重要だと感じられたポイントは何でしょうか?
人類が月や火星にまで足を延ばすことは、技術的にハードルが高いチャレンジだろうと思っています。特に火星は、距離が大きな障害になると考えています。ISSでは、窓の外にすぐ地球が見えます。何か重要な機械が壊れても、すぐに代わりのものを打ち上げてもらえますし、たとえ食料が1回届かなくても、別の便に振り替えて届けてもらうこともできます。この距離の近さを武器にした確実な運用が可能になっていますが、地球から片道8ヶ月かかる火星では同じようにいきません。補給の機会も能力も今より限られてくるため、それが運用の難しさに直結するだけでなく、宇宙飛行士の精神面にも影響してくるでしょう。ただ、具体的にどう影響するのかは、自分でも想像がつきません。何かあったら助からないかもしれないという緊張感に常にさらされながら火星まで旅をするとなれば、宇宙飛行士の精神的負荷は今より桁違いに大きいはずです。ですから、今私たちが持っている技術はさらに信頼性を上げていく必要がありますし、宇宙飛行士のメンタル面のケアについても、考えていかなければならない課題だと感じています。

ー火星探査ではメンタル面が課題とのことでしたが、それを克服するための研究は行われているのでしょうか。また、今回の滞在中の実験には、月や火星探査に向けた課題に関するものも含まれていたのでしょうか。
「マーズ500」のように、地上の隔離施設で少人数のチームが500日間生活するアナログミッションは実際に行われていて、有効なデータをもたらしていると思います。ただ、そういったテストフィールドで500日間過ごすのと、命の危険があるというストレスと闘いながら500日間過ごすのとでは、大きな隔たりがあるでしょう。精神的ストレスをリアルに模擬した研究は、まだ行われていないのではないでしょうか。私自身、ISSに何百日いても怖いと思ったことはありませんでしたが、本当に火星に行くとなると想像を絶する感じがあるので、これからの大きな課題だと思います。
月や火星に向けた研究としては、宇宙飛行士のメンタル面と肉体面、両方のサポートが重要です。そして何より大事なのは、今持っている技術の信頼性を向上させることだと思います。ISSでは色々なものが日常的に壊れますが、他の機能で代替したり、自分たちで直したり、工夫を重ねてデータを蓄積しています。それらを活用した技術の底上げは欠かせないと感じています。
ー今回、船長を務められましたが、閉鎖環境の中でクルーをまとめるために、船長として心がけたことを教えてください。
心がけていたことは2つあります。1つは、クルー全員でのコミュニケーション機会を作ることです。ISSは複数のモジュールで構成されていて、宇宙飛行士はミッションによってバラバラにわかれて作業します。すると、生活空間もわかれがちでコミュニケーションの機会が減ってしまいます。そこで週に1回は必ずみんなで集まって夕食を共にするようにしていました。もう1つは、クルーにとって節目となるイベントを大事にすることです。誰かが誕生日を迎えたり、ISS滞在日数が区切りを迎えた記念日などは、必ずみんなで祝うようにしていました。
ー一般の方が宇宙に行ける時代が近づいていますが、前回の2016年と比べて、軌道上での生活がしやすくなった点があれば教えてください。
前回と比べて質が向上したと感じたのは、食事とネットワークです。
まず食事ですが、宇宙日本食だけでなく、アメリカやロシアの宇宙食も全体的にバラエティが豊かになりましたし、味も向上したと感じます。補給機が来るたびに新鮮な食料も届くので、ピザを作ってみんなでピザパーティをしたこともありました。前回は食事が大きなストレスの一つだったのですが、今回はかなりストレスフリーな5か月間でした。
それからネットワークに関しては、今のISSは地上のインターネット接続に近い環境が実現されていて、YouTubeのような動画サイトもほぼストレスなく見られます。これは一番大きな改善点だったかもしれません。9年前と比較すると、日常生活から来るストレスはほとんど感じず、5か月間があっという間に過ぎていったという感覚でした。
ーISSでやり残したことがあれば教えてください。また、今回の経験を踏まえて、今後のキャリアについてどのようにお考えでしょうか。
やり残したこととしては、船外活動が挙げられます。打上げ前から「機会があれば船外活動を」と申し上げてきた通り、私にとって非常に大きな希望の一つでした。残念ながら今回のミッションでは機会に恵まれませんでしたが、それに代わるものとして、ISSの船長という大役を果たすことができました。これは何事にも変えられない経験になったと思います。二兎を追うものは…ではないですが、私は船長としての役割をやり遂げ、仲間には船外活動の機会を与えることができたので、自分の中では満足しています。
今後についてですが、地球に帰ってきてまず感じたのは、今回の経験と学びを後進や地上のエンジニアの方々にしっかり引き継ぎ、そして国民の皆さんに自分の体験を伝えなければという思いでした。その役目をきちんと果たした上で、宇宙飛行士の一人としてアルテミス計画に貢献していきたいと思っています。月に行った人類は本当に一握りですが、少なくともそれに挑戦する資格はあると思うので、そのことに感謝しつつ、これまでの経験を全てぶつけるつもりで、月を目指したいと考えています。

ーCIMONとInt-Ball2で行なわれたミッションの内容について教えてください。
今回はあくまで技術的な実証だったので、何か意味のある作業を実施したというわけではありませんが、内容としては物探しのミッションです。まず、仲間のクルーが「きぼう」の中にいろいろなものを隠しておきます。私は別の部屋にいて、CIMONに対して命令を送ります。その命令がCIMONから「きぼう」の中にいるInt-Ball2に届くと、Int-Ball2が「きぼう」の中を動き回ってものを探すというタスクを実行しました。この時、私からCIMONに出す命令としては、前後、左右、上下など動きの指示です。「首を右に振って」「上を向いて」という具合に、一つひとつ言葉で伝えると、CIMONがそれを解読してInt-Ball2に指令を通信で送るという流れです。
ー9年前と比べて随分ものが増えたとのことですが、前回と今回で、ISSや「きぼう」のフェーズはどう変わったのでしょうか。
前回の2016年は、ISSが完成して稼働し始めて数年という段階で、成熟期に差し掛かったあたりだったと思います。その後さらに9年を経た今回の2025年は、かなり成熟した段階にあると感じました。具体的には、それまで宇宙飛行士が実際に手を動かしてやっていた作業が、遠隔化・自動化されていました。実験についても、以前は大きなラックの中で行っていたものが、今回はお弁当箱ほどの小さな実験装置で済むようになり、その中に顕微鏡やカメラ機能まで搭載されています。省スペース化だけでなく、全てにおいて効率性が向上していることを実感しました。ISSに人が滞在するようになって25年という節目を間もなく迎えます。今後、2030年にISSが退役を迎えたとしても、この間に積み重ねてきた知見が失われてしまうのは人類全体にとって大きな損失だと思うので、しっかりと民間の商業宇宙ステーションにつないでいかなければならないと感じています。
ーポストISSは民間主導になるとのことですが、民間が成功するために必要な要素や課題は何だとお考えでしょうか。
いちばん大きな課題はコストだと思います。民間企業がやるということは、ビジネスとして収支が成立しなければなりません。コストを下げて、そこからいかに有益なものを作り上げられるかが至上命題になってくるでしょう。今、ISSに民間企業が自分たちで宇宙飛行士を送り込む商業ミッションも行われていて、私の滞在中にもアメリカのアクシオム・スペース社のミッションがありました。宇宙開発は、長い目で見ると人類のバトンリレーだと思っていますが、これまで国が中心になって運営してきたISSの役割を、すべて一気に民間にシフトさせるのは難しいでしょう。今回の彼らのミッションは、ISSをテストベッドとして使ってもらうという意味で象徴的だったと思います。
ISSに長期滞在する私たちがマラソンを走るような感覚で宇宙に行くのに対し、彼らは100m走を走るつもりで来ています。そのため、生活のリズムや仕事への臨み方が全然違います。異なる2つのグループが一緒になると問題点も出やすいのですが、彼らは非常にモチベーションの高いクルーでしたし、私たちも今後こういったミッションが増えてくるという覚悟のもと、お互いに良い関係で過ごせたのは印象的でした。
ー10月21日にHTV-Xの初号機が打ち上がりますが、現場の宇宙飛行士の視点で、将来的な発展のビジョンがあれば聞かせてください。
スペースX社を見ていて強く感じたことですが、彼らはクルードラゴンという有人宇宙船と、カーゴドラゴンという補給機の2バージョンを持っていて、基本設計はほぼ共通です。そのため、この2種類をどんどん打ち上げることで、双方にプラスになる効果を生み出しています。カーゴミッションで出た不具合を一つひとつ潰して安全性を高め、人が乗れる設計に変えている。そして有人宇宙船で積み上げた実績を、またカーゴドラゴンにフィードバックしている。その相乗効果で非常に信頼性の高い機体を作り上げているのです。この、ミッションを数多く持つ点に非常に強みを感じるので、日本も「こうのとり」「HTV-X」という補給機ミッションによる知見をもっとたくさん蓄えることで、将来的に日本独自の有人宇宙船の開発につながっていくような、実証的な意味合いを持つミッションにできればと、個人的には思っています。
基幹技術を持っている国は、国際協力の中での発言権が高まりますし、存在感が大きくなります。今、残念ながら日本は有人輸送については他国の力に頼っている状態ですが、将来、日本が人を宇宙に送り届ける技術を持つことは、大きな競争力になると思っています。

大西宇宙飛行士会見終了の挨拶(抜粋/要約)
皆さん、今日は貴重な時間を割いて、この記者会見にご参加くださいまして本当にありがとうございました。こうやって自分が経験してきたことを、たくさんの方々に紹介させていただくというのは、私たち宇宙飛行士が負っている大きな使命だと私は思っています。今回の帰国中には、そういった活動に力を注いでいきたいと思っています。具体的には、11月8日に開催される筑波宇宙センターの特別公開イベントで登壇させていただく予定です。また、11月14日には都内でミッション報告会を計画しています。11月8日の特別公開は、小さなお子さんたちに科学に対して興味を持ってもらう会になると思います。それが日本という国にとって大きな意味を持つことだと私は考えています。また11月14日のミッション報告会の場に、たくさんの大人の方に足を運んでいただければと思います。私自身も今回のフライトで1つの区切りをつけた後、また次の目標に向かって、いちから頑張っていこうと思いますので、引き続き私たちJAXAの宇宙開発について応援をいただけると嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。
会見には、15社19名のメディアが参加し、他にも多くの質問が寄せられました。
その様子は、JAXA YouTubeチャンネルでアーカイブされていますので、ぜひご覧ください。
JAXA 大西卓哉宇宙飛行士 帰国記者会見(YouTube:1時間13分35秒)
帰還に関するレポートは以下のトピックスで振り返ることができます。
※本文中の日時は全て日本時間